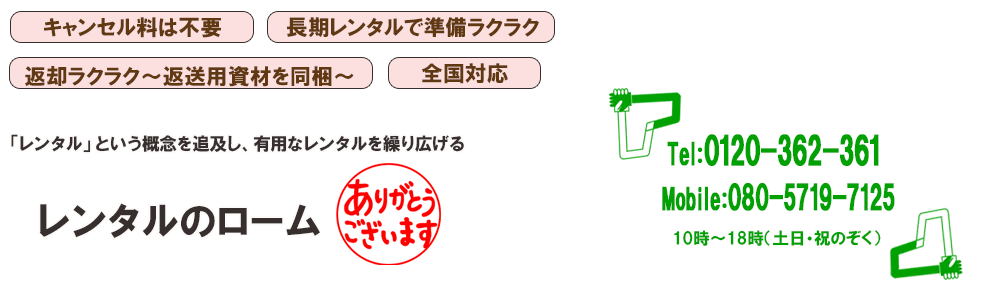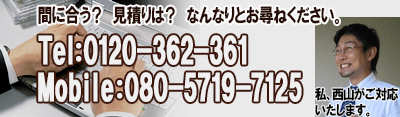倉庫の扉を開けると、埃の匂いがした。
父が亡くなって三ヶ月。四十九日も終わり、ようやく遺品整理に手をつける気になった。正確に言えば、母に頼まれたのだ。「お父さんの倉庫、あんたが見てくれん?」と。兄は東京、妹は結婚して熊本。福岡市内に住んでいる自分が、一番近い。
久留米の実家には、家とは別に小さな倉庫がある。父が生前「男の城」と呼んでいた場所だ。工具、釣り道具、キャンプ用品。そして、得体の知れないガラクタ。
目が暗さに慣れてくると、奥に大きな影が見えた。
扇風機だった。
業務用の、大型扇風機。直径五十センチはあろうかという羽根。ステンレスのガードは錆びているが、形はしっかりしている。高さは自分の胸くらいまである。
なぜこんなものが。
記憶が、ふいに蘇った。
小学五年生の夏。父はPTA会長をしていた。
あの年の夏祭りは、体育館で行われた。前日から準備があり、父は何度も学校に通った。自分も何度か連れて行かれた。
「暑かねえ」
体育館は蒸し風呂のようだった。窓を開けても風は入らない。天井だけが高くて、熱気がそこに溜まっていた。
父がどこからか調達してきたのが、この扇風機だった。レンタルだったのか、誰かに借りたのか。今となってはわからない。
スイッチを入れると、風が起きた。
体育館の空気がぐわんと動いた気がした。子供たちが「おー」と声を上げた。大人たちは笑った。父も笑っていた。
その風の中心に、自分たちはいた。
「これ、動くんかな」
独り言を言いながら、コンセントを探した。倉庫の奥に、埃をかぶったタップがある。扇風機のプラグを差し込み、おそるおそるスイッチを押した。
沈黙。
やはりダメか、と思った瞬間、羽根がゆっくりと回り始めた。
風が来た。
古い倉庫の空気が動く。埃が舞う。そして、匂い。何の匂いかわからないが、懐かしい匂い。
目を閉じた。
あの頃、世界は完璧だった。
父がいた。母がいた。兄がいて、妹がいた。叔父も叔母もいて、祖父母も健在だった。いとこたちと走り回り、夏祭りでは夜更かしを許された。
近所には友人がいた。学校から帰ると、誰かしらが外にいた。ゲームなんかしなくても、日が暮れるまで遊べた。
全員が、同じ世界にいた。
同じ空気を吸い、同じ風に吹かれていた。
今、父は死んだ。
兄とは年に二回、盆と正月に会うだけだ。妹とはLINEでたまにやりとりするが、電話で話すことはほとんどない。
叔父は三年前に脳梗塞で倒れ、施設に入っている。見舞いに行ったのは一度きりだ。
いとこたちとは、父の葬儀で久しぶりに顔を合わせた。子供の頃はあれほど親しかったのに、何を話せばいいのかわからなかった。
近所の友人たちは、ほとんどが久留米を離れた。自分も福岡市内に出た。たまに同窓会の連絡が来るが、行ったことはない。
みんな、生きている。
死んだのは父だけだ。他のみんなは、ちゃんと生きている。
なのに、世界は、確実に、壊れている。
いつ壊れたのか。
大学進学で久留米を出た時か。就職で福岡市内に住み始めた時か。結婚した時か。結婚しなかったからか。
違う。どれも違う。
壊れたのではない。壊れていったのだ。少しずつ、少しずつ。気づかないうちに。
子供の頃、世界の真ん中には何かがあった。それが何かはわからない。家族の食卓だったかもしれない。夏祭りの夜だったかもしれない。体育館を吹き抜けた、あの風だったかもしれない。
真ん中に何かがあったから、自分たちはそこに集まれた。
今、真ん中には、穴が空いている。
でも、空洞ではないのかもしれない。
あの頃、真ん中にあったものは、散らばった人それぞれの中に移ったのだ。兄の中に、妹の中に、叔父の中に、自分の中に。みんなが少しずつ持ち帰った。
だから真ん中は空っぽに見える。でも、集まれば、また現れる。そういうものなのかもしれない。
風が止まった。
見ると、扇風機は静かに羽根を止めていた。モーターがついに力尽きたのかもしれない。あるいは、接触不良か。
倉庫が急に暑く感じた。
プラグを抜き、扇風機を見つめた。錆びたガード。色褪せたスイッチ。三十年近くここにあったのか。
父は、なぜこれを捨てなかったのだろう。
母に聞いてみようと思った。
玄関を開けると、母は台所にいた。「終わった?」と聞かれ、「まだ」と答えた。
「あの扇風機、なんで取っとったと?」
母は手を止めた。少し考えて、言った。
「あれね、お父さんが買い取ったとよ」
「買い取った?」
「レンタルやったらしいけど、気に入ってね。返す時に、譲ってもらえんかって頼んだら、もう古いけんっていうて、安う売ってもらえたんやって」
「へえ」
「あんときの夏祭り、楽しかったもんねえ」
母は遠い目をした。
「みんなおったねえ。あんたのお父さんも、おじさんも、ばあちゃんも。子供らもみんな元気で、走り回りよったねえ」
「うん」
「あの扇風機ば見ると、思い出すっちゃないと?お父さん」
倉庫に戻った。
扇風機の前に立ち、もう一度プラグを差した。スイッチを入れる。
羽根が回り始めた。さっきより弱い風。でも、確かに風。
父は、この風を残したかったのだろうか。
あの日、体育館の真ん中で起きた風。みんなを繋いでいた風。その風が吹く限り、世界はまだ続いていると、そう思いたかったのだろうか。
わからない。
九月になれば、この扇風機はまた倉庫の奥にしまわれる。
来年の夏、自分はこれを出すだろうか。それとも、処分してしまうだろうか。
兄に連絡しようと思った。用件はない。ただ、電話してみようと思った。妹にも。できれば、叔父の見舞いにも行こう。
世界は再構築できるのか。
わからない。たぶん、同じ形には戻らない。戻らなくていいのかもしれない。
ただ、風を止めてはいけない気がした。
穴を塞ぐことはできなくても、その周りに人が集まれる理由を、どこかに作っておかなければ。
父がそうしたように。
八月のその日、容赦ないはずの日差しが何か言いたげだった。