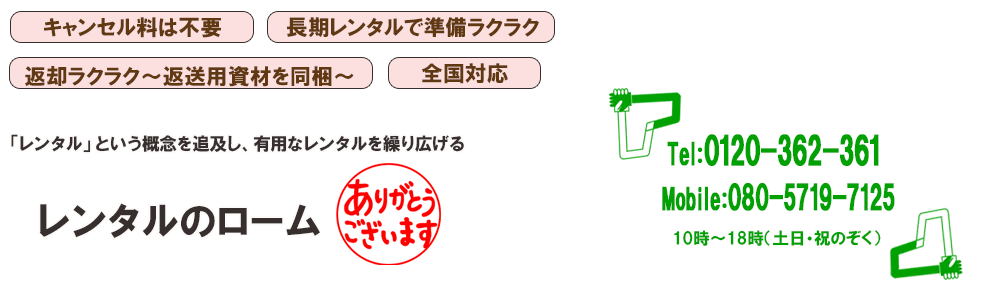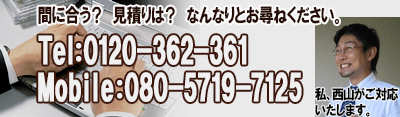タンクは沈黙しているが、その沈黙こそが、すべてを支えているのである。
第一章 失われたタンク
福岡の冬は意外に乾燥する。博多湾からの湿った風は、都市部に届く頃には既にその潤いの多くを失っている。
美咲は毎朝、寝室の加湿器の音で目を覚ます習慣があった。微かな振動音と、時折聞こえる水の音。それが彼女の一日の始まりを告げる静かな合図だった。
しかし、その朝は違った。
「あれ?」
いつものように手を伸ばして加湿器を確認すると、本体は動いているのに霧が出ていない。LEDパネルには「水不足」の赤いランプが点滅していた。
タンクを確認すると、昨夜確かに満タンにしたはずの水が空になっている。おかしい。タンクに穴でも開いたのだろうか。
美咲は予備のタンクを探したが、見つからない。確か二つあったはずなのに、一つしかない。
「まあ、一つあれば十分よね」
そう呟いて、彼女は水を満たしたタンクを取り付けた。
第二章 違和感の連鎖
その日から、美咲の生活に微細な変化が起こり始めた。
まず、肌の調子が悪くなった。いつも使っている化粧水の浸透が悪く、ファンデーションが粉っぽく浮く。
次に、喉に違和感を覚えるようになった。天神のオフィスで同僚と話していても、声がかすれがちになる。
「風邪の前兆かな」と思いながらも、熱はない。体調に問題はないはずなのに、何かが微妙にずれている。
加湿器は相変わらず一日中動いているのに、部屋の空気はなんとなく重い。以前のような、しっとりとした心地よさがない。
一週間が過ぎた頃、美咲は気づいた。加湿器の稼働時間が短くなっている。タンクの水の減りが異常に早いのだ。
「故障かしら」
福岡市内の家電量販店で点検を依頼すると、店員は首をかしげた。
「機械自体には問題ありませんね。ただ…タンクが一つしかないようですが、この機種は本来二つのタンクで最適化されているんです」
「二つ?」
「はい。一つは基本的な加湿を担当し、もう一つは湿度の微調整を担当する。両方があって初めて、理想的な湿度環境を作り出せるんです」
美咲は愕然とした。彼女が紛失したと思っていたタンクは、実は加湿器の重要な構成要素だったのだ。
第三章 支えの発見
その夜、美咲は自分のアパートで一人考えていた。中洲の夜景を眺めながら、加湿器の話が妙に心に引っかかっていた。
タンクが一つなくなっただけで、全体が機能しなくなる。
それは、彼女の人生にも当てはまるのではないだろうか。
思い返せば、最近調子が悪いのは肌や喉だけではない。仕事への集中力も落ちている。同僚との会話も以前ほど弾まない。恋人との関係もぎくしゃくしている。
でも、それらは全て「最近疲れてるから」で片付けていた。
美咲は携帯を取り出し、母親に電話をかけた。
「お疲れさま、美咲。元気?」
母の声を聞いた瞬間、美咲は涙が出そうになった。
「お母さん、私…最近なんか調子悪くて」
「どうしたの?体調?」
「体調じゃないんだけど…なんていうか、全部がうまくいかない感じ」
電話の向こうで、母は静かに聞いていた。
「美咲、最近いつ実家に帰った?」
考えてみると、一ヶ月以上帰っていない。以前は週に一度は顔を出していたのに。
「もしかして、それかもしれない」母は優しく言った。「あなたにとって実家は、心の加湿器のタンクみたいなものかもしれないわね」
第四章 見えない支えたち
翌週末、美咲は久しぶりに実家に帰った。福岡市の郊外、昔から住み慣れた住宅地の小さな家。
玄関を開けた瞬間、懐かしい匂いに包まれた。母の手料理の匂い、父の読みかけの新聞、飼い猫のミケの毛布。
「おかえり」と母に抱きしめられたとき、美咲は自分がどれだけこの「当たり前」に支えられていたかを実感した。
夕食の準備を手伝いながら、母と他愛のない会話を交わす。父は相変わらず新聞を読みながら、時々的外れなことを言って笑わせる。
その夜、久しぶりに実家のベッドで眠った美咲は、翌朝すっきりと目覚めた。
「なんか、調子いい」
肌の調子も、喉の調子も、不思議と改善している。
第五章 タンクの意味
月曜日、オフィスに戻った美咲は加湿器のタンクを買い足した。そして、それを取り付けながらふと考えた。
人にも、見えないタンクがたくさんある。
家族との時間、友人との笑い、一人で過ごす静かな時間、好きな音楽、散歩する公園、行きつけのカフェ。それら一つ一つが、心の加湿器を支えるタンクなのかもしれない。
どれか一つが欠けても、すぐには気づかない。でも、確実に全体のバランスが崩れていく。
美咲は同僚の田中さんを見た。最近彼が元気がないのは、転勤してきたばかりで、まだ「心のタンク」を見つけられていないからかもしれない。
「田中さん、今度の週末、博多ラーメン食べに行きませんか?私、おいしいお店知ってるんです」
田中さんの顔が明るくなった。
「本当ですか?ありがとうございます」
第六章 沈黙の声
その夜、美咲は完璧に調整された加湿器の音を聞きながら眠りについた。二つのタンクが静かに、でも確実に部屋を潤している。
朝起きると、空気がしっとりと肌に馴染んだ。喉の調子も完璧だ。
鏡を見ると、一週間前とは明らかに違う自分がいた。肌に艶があり、目に輝きがある。
加湿器は何も言わない。タンクも、その存在を主張することはない。でも、その沈黙こそが、すべてを支えている。
美咲は携帯を取り出し、母にメッセージを送った。
「お母さん、ありがとう。また今度の週末、帰るね」
すぐに返事が来た。
「いつでもおかえり。あなたのタンクはいつでもここにあるから」
美咲は微笑んだ。見えない支えは、決して声高に存在を主張しない。でも、それがあるからこそ、私たちは毎日を生きていける。
加湿器のタンクが一つなくなったように、人生からも大切なものが知らずのうちに失われることがある。でも、それに気づいたとき、私たちは改めてその大切さを知る。
福岡の街を見下ろしながら、美咲は思った。この街にも、きっと無数の見えない支えがある。掃除をする人、電車を運転する人、コンビニで夜中まで働く人。その一人ひとりが、誰かの加湿器のタンクなのかもしれない。
そして私も、誰かのタンクになっているかもしれない。
加湿器は今夜も静かに働いている。二つのタンクが、その役割を黙々と果たしながら。
完
—